少年野球の指導あたって、自身が読んだ本をオススメ順にまとめています。
私個人の価値観に左右される部分はありますので、必ずしも順位通りに良書であるという訳ではありませんが、どれから読んでいこうかと考えている方にとって参考になるランキングになればと思っています。
特に「”絶対読んだほうがいい”に分類した書籍を選べば指導にあたって大事な部分は押さえられる」と言えるようにまとめていきたいと思います。
現在で読んだ冊数は19冊です(2025年6月26日時点)。
※書籍タイトルにはAmazonのリンクを貼り付けています。
- 評価内容
- ランキング一覧
- 絶対読んだほうがいい:1位〜6位
- 読んで損はなし:7位〜11位
- その他:12位〜19位
- 12位:『コントロールの極意』吉見一起・著(2022/5/27)
- 13位:『高校野球界の監督(スペシャリスト)がここまで明かす!投球技術の極意』大利実・著(2021/7/20)
- 14位:『小学生からはじめるウエートトレーニングあり⁈なし⁈ 筋トレすると背が伸びないはもう古い!!』大浜海・著(2024/5/25)
- 15位:『DVDで差がつく! 小学生の野球 最強のポイント55 (まなぶっく)』大前益視・監修(2018/3/5)
- 16位:『野球データ革命』森本崚汰・著
- 17位:『トクサンTVが教える 超ピッチング講座』アニキ・著(2019/11/22)
- 18位:これで差がつく! 勝つ!軟式野球 上達のコツ50 (コツがわかる本!)名古屋光彦・監修(2018/6/5)
- 19位:『野球選手を育てる教科書 少年野球』
- さいごに
評価内容
大きく5つの項目を総合的に評価してランキングを作成しています。
※当初は各項目に点数をつけてランキングを作成していましたが、主なテーマが書籍によって様々であるため、実際にオススメしたいと思う順番と点数の順位が一致しなかったため、最終的な順位のみでまとめていきます。
コストパフォーマンス
いい本、良い内容のものはお金を出してでも手に得るべきだと考えていますが、内容とコストのバランスも踏まえた上で判断していきます。
「この本はお金を出してでも読む価値がある!!」と思えたかどうかという感覚です。
内容の分かりやすさ
内容の分かりやすさ、読みやすさです。難しい言葉が並んでいたり、難しい話ばかりだと中々読み進められないし、自分の中に内容を落とし込みにくいと思います。
内容の充実度合い、具体例
情報量、ボリュームです。内容が充実している方が多くの学びを得られる可能性が高まると思っています。また、内容の量だけでなく、かゆいところに手が届くところまで踏み込まれていると、誤った解釈をしづらくなり、自身の学びにつなげやすくなると思われます。
根拠、明確性
「なんとなくこう思う。」という内容ではなく、具体例や根拠を示して、明確な結論を出している方がより信頼ある情報と考えられます。経験談に基づく内容でも、たった1件の例外を取り上げている可能性があります。参考にするにあたって、データや根拠が明確で、信頼性の高いと思われる結論を話しているかは最重要であると思っています。
実践のしやすさ
根拠の次に大事したいポイントは実践しやすいかどうかです。本は読むだけで終わっては意味がありません。自身の指導に活かしてこそ意味を持つと思っています。そのため、再現性があったり、今すぐにでも取り組めるものがあれば、より実践的な内容であると思います。
ランキング一覧
ランキング形式にしていますが、「絶対に読んだほうがいい」「読んで損はなし」「その他」の3分類に分けてまとめています。
個人的に「1位〜6位:絶対に読んだほうがいい」「7位〜11位:読んで損はなし」と思います。
それぞれの書籍について簡単な感想をまとめているので、参考にしていただけたらと思います。
※絶対に読んだほうがいいは気持ち的には全て同率1位です。
絶対読んだほうがいい:1位〜6位
1位:『野球の教え方、教えます! (パーフェクトレッスンブック)』大石滋昭・著(2016/6/30)
第1位は『野球の教え方、教えます! (パーフェクトレッスンブック)』大石滋昭・著です。
元プロ野球選手の大石滋昭(おおいししげあき)氏が「野球の教え方」について書いた1冊になります。
子どもたちがやってしまいがちなミス、集中力が切れず大事なことが心に残る教え方など、野球指導の現場を数多く経験している著者ならではの切り口で、わかりやすく解説しています。
本書の内容は全日本野球協会が認定する野球指導者資格である「公認野球指導者 基礎Ⅰ U-12」の動画教材としても使用されているものです。
私自身2022年にこの資格を取得し、その際に学んだ本書の内容がとても勉強になり、その後の指導(特に低学年の指導)に活きていると実感しています。
個人でもチームでも即実践できる行き届いた解説
指導風景や各動作の写真に加え、子どもがより理解しやすくなる声の掛け方や、指導者と選手の位置関係まで詳しく説明されています。
複数人で練習する時に効率が良くなる工夫もあり、個人はもちろん、チームでも即実践可能と思えるところまで解説されていました。
指導者も選手も0から1を学べる
まだ自分の身体を器用に動かすことが難しい小学生低学年の段階ではどのように教えていくのかなど、子どもがより理解しやすい指導をするための工夫や、ポイントが押さえられています。
何からどのように教えていいか分からない指導者が、未経験の選手に教えることができるようになる1冊だと思いました。
「打つ、投げる、捕る、走る、メンタル」の野球の基本的なプレーの0から1を身につけるための最初の1歩が詰め込まれています。
低学年の子ども教えることが苦手な指導者には特に読んで欲しい
指導者の中には低学年になればなるほど教えるのが苦手だという意識がある人もいると思います。
「楽しく過ごしてもらう事が第一だけど、せっかく練習に来たのにワイワイして終わりでいいのだろうか?」
「高学年になるまでに少しでもレベルアップさせてあげることができれば、もっと活躍して野球を楽しめただろうな」
「低学年に教えるって何をするの?」
というような事を思ったことがある指導者はぜひ読んでみて欲しいと思います。
2位:『新しい少年野球の教科書~科学的コーチングで身につく野球技術~』川村卓(かわむらたかし)・著
第2位は『新しい少年野球の教科書~科学的コーチングで身につく野球技術~』川村卓(かわむらたかし)・著です。
まさに少年野球指導者として教科書となる一冊だと思いました。
少年野球に特化した内容で、指導するにあたって必要な知識から練習方法まで体系的にまとめられています。
内容を考えても、一読の価値は大いにあると思います。
わかりやすい
研究に基づいた内容のため専門用語も出てきますが、分かりやすく言い換えてくれているため難しいと思う内容はありませんでした。
解説内容には画像も含まれているため、文章だけでは分かりにくいところもカバーされています。
内容も充実
子どもの発達段階に基づいて、「投げる、守る、打つ、気持ちや身体の変化」について分けて解説されています。
練習方法や意識してほしいポイントなどが数多く書かれており「取り組んでみよう」と思う練習内容や、「意識してみよう」と思う視点が必ず見つかると思います。
根拠もあり、明確な内容が多い
研究に基づく内容で、根拠ある内容が基本となっているので信頼度の高い情報と思いました。
「経験上~となることが多い」という表現で、まだ解明されていない内容や、効果は人によると言った内容もありますが、指導方針の参考になると思います。
少年野球の現場で実践しやすい
本書は少年野球に取り入れるならという視点で書かれているため、チームに取り入れるイメージのしやすい内容も多くありました。
実際にコントロールをよくするために行う「パラボリックスロー」という玉入れのような練習法については、実践してみて大好評でした。
他にも子どもたちが楽しみながらレベルアップできる練習法も紹介されているので、実践しやすい内容と思います。
3位:『野球少年のやる気と能力を最大限に引き出す 魔法のアドバイス』立花龍司・著(2016/9/1)

第3位は『野球少年のやる気と能力を最大限に引き出す 魔法のアドバイス』立花龍司・著(2016/9/1)です。
日本プロ野球で初のコンディショニングコーチとなり、メジャーリーグ(ニューヨークメッツ)でもコーチを務めた経験のある立花龍司氏の著書です。
専門的な知識で、野球選手のさらなるレベルアップのために様々な著書を出されていた立花氏ですが、本書は「ひとりでも多くの子供に野球を大好きになってほしい」という思いから、野球を良く知らない保護者でも子どもにアドバイスができる、サポートができることを目的て書かれています。
同じ”絶対読んだほうが良い”に分類している『『球導』野球少年を正しく導くためのアドバイス』年中夢球・著も技術書ではなく大人の在り方について書いているという点で同じようなコンセプトと思いましたが、立花氏の書籍の方が大人と子どもの1対1の関わり方に焦点を当てた内容だと感じました。(年中夢球氏の書籍はチームに所属する指導者としての振る舞いにより焦点を当てた内容と思います。)
子どものやる気を引き出すためのヒントがたくさん
指導者や保護者は子どもに野球をうまくなって欲しいと思うものだと思います。
しかし、本書では繰り返し大切なのは「子どもが野球を好きであること」ということが伝えられています。
ざっくりと言えば、野球が好きであれば子ども自身が自ら進んで上手くなっていくと言う考えです。
そのためにできる大人の役割として、「野球の教え方」ではなく「子どもとの関わり方」に焦点を当ててやる気を引き出すための行動のヒントがたくさんある一冊です。
実際の立花氏と息子さんとの関わり方も一例として出てきますが、教え方よりも関わり方の大切さが分かるエピソードがたくさんあります。中でもバッティングセンターでのエピソードは私とっては衝撃的で驚かされました。
本書の内容を実践するのに特別なスキルはいらない
本書は「野球を良く知らない保護者」という前提で書かれていることもあり、特別なスキルがなくても実践できる内容ばかりです。
強いて言えば、親のエゴよりも子どもの気持ちを尊重するということぐらいで、その気持ちさえ持てれば今すぐにでもできることが多くあると思います。
具体的なシーン別の関わり方についても書かれている
「大事な場面でエラーをしたとき」「三振をしたとき」「自分が一番だと天狗になっているとき」など
対応に迷いがちなシチュエーションを取り上げて、どう関わるのが良いと思うかについて、選手の性格別や根拠を交えて立花氏の考えが書かれています。
4位:『『球導』野球少年を正しく導くためのアドバイス』年中夢球・著

第4位は『『球導』野球少年を正しく導くためのアドバイス』年中夢球・著です。
本書は練習法やテクニックについて書いている技術書ではありません。
指導者としての子どもとの接し方や、心の持ちよう等の、人としての土台に当たる部分について焦点を当てて書かれています。
同じ”絶対読んだほうが良い”に分類している『野球少年のやる気と能力を最大限に引き出す 魔法のアドバイス』立花龍司・著も技術書ではなく子どもとの接し方や大人の振る舞いにについて書いているという点で同じようなコンセプトと思いましたが、年中夢球氏の書籍の方がチームに所属する指導者としての振る舞いにより焦点を当てた内容だと感じました。(立花氏の書籍は大人と子どもの1対1の関わり方に焦点を当てた内容と思います。)
エピソードを中心としてイメージしやすい
実際のエピソードを踏まえた内容で、指導者をしている人にとってはとてもイメージしやすい内容だと思います。
筆者の意見を中心に書かれていますが、「そうだな」と腑に落ちる内容も多く、シンプルで分かりやすいです。
著者の主張は明確でわかりやすい
研究などに基づいた内容ではなく、筆者の経験則や主張を基に書かれていますが、具体例もあり、主張する内容は明確だと思います。
主観による意見が中心ですが、個人的には納得できる内容が多く含まれています。
自分の思う指導者像を見つめ直せる1冊
「こうあるべき!こうしなければならない!」という押しつけではなく、「こうあるべきではないでしょうか?」という問いかけのようなスタンスであり、自身の考えを見直したり、指導者としての振る舞いについて、自分なりの軸となる部分ができるきっかけとなるのではないかと思います。
5位:野球 肩・ひじ・腰の鍛え方と治し方: 思いきり野球ができる身体づくり 自分でできるトレーニングとフォーム修正 野球の上達と障害の予防は両立できる!間瀬泰克,坂田淳・著(2023/3/1)
第5位は『野球 肩・ひじ・腰の鍛え方と治し方: 思いきり野球ができる身体づくり 自分でできるトレーニングとフォーム修正 野球の上達と障害の予防は両立できる!』間瀬泰克,坂田淳・著です。
野球選手の「肩・ひじ・腰」の痛みについて、①なぜ痛みが起こるのか②痛みが発症している場合、しっかり治すためにはどうしたらいいのか③予防するために必要なことは何なのか、について医学的根拠に基づいてまとめられている1冊です。
痛みが発生する部位、同じ部位でも症状別の対処法、怪我防止のためのトレーニングや柔軟性のチェック項目など、これ1冊で基本的な知識は補えているのではないかと思いました。
より高いレベルでプレーしたいと思っている選手や、指導をする立場の人にとっては必読書であると思います。
写真とイラストでわかりやすい
本書は筋肉の部位などについて専門的な内容がまとめられていますが、全ての説明で写真やイラストを使っているため、とても理解しやすいです。
必要なトレーニングやストレッチの写真、痛みの原因を探るためのフローチャートもあり、自分が気にしている内容をピンポイントで探しやすいと思いました。
怪我防止だけではなくレベルアップにも
長く野球をプレーしたい人はもちろんですが、紹介されているエクササイズは全てプレーに必要な動作や可動域に直結するものなので、プレー技術の向上にも間違いなく繋がります。
野球の動作に必要な身体機能の土台を形成するために、本書のトレーニングは大いに活用できると思います。
少年野球に当てはめても、トレーニングはこういうことを地道にできたら、怪我の防止にもなるし、できないことができるようになったり、急激なレベルアップにも繋がると感じました。
実践のハードルも低く取り組みやすい
シンプルな分実践すること自体のハードルは低いので、やろうと思えばできるものばかりです。
紹介されているメニュー自体は、シンプルで地味なことが多いので、特に少年野球だと面白くはないと思われるかもしれませんが重要度は高いと思います。
6位:『子どもの足がギュンッと速くなるキッズラントレ』秋本真吾・著
第6位は『子どもの足がギュンッと速くなるキッズラントレ』秋本真吾・著です。
野球を専門的に取り上げている本ではありませんが、走る能力は野球においても大事な要素のひとつになります。
本書は子どもが速く走れるようになるための姿勢やトレーニングメニューなどをまとめた1冊になっています。
小学生から取り組める内容
本書は速く走るために必要なトレーニングがまとめられていますが、全て小学校から取り組める内容になっています。
また、それぞれのメニューに5段階で強度が示されているので、強度の低いものから選んで取り組んでいけます。
それぞれのトレーニングメニューも写真付きで説明されているのでわかりやすいです。
実際に走るのが速くなった
私が指導した子どもの1人に、学校のクラスでも走るのが遅い方で、走ること自体に苦手意識がある子がいましたが、できる内容をコツコツと積み重ねた結果、クラスのみならずチームでもトップを争うぐらい走れるようになり、走ることへの苦手を払拭したという例もあります。
また、中学生まで50m走のタイムが年齢平均以下だった子が平均以上のタイムを出せるようになった等、指導している中でも効果を実感しています。
読んで損はなし:7位〜11位
7位:『マンガで超レベルアップ! 少年野球 練習編』西東社編集部・編(2019/12/5)

第7位は『マンガで超レベルアップ! 少年野球 練習編』西東社編集部・編です。
フルカラーの漫画&図解で読みやすい!小学生の選手本人が読む技術書としても◎
本書はすべてのページがカラーになっており、漫画と図解でまとめられているので読み進めやすいです。
漫画のストーリーの中で練習内容が紹介され、その練習内容について改めて解説のページがあります。
本全体が気軽に読み進められるため、小学生の選手本人が読んで実践してみる1冊としても良いと思います。
工夫された練習内容で新たな気づきがあるかも
本書で紹介されているメニューは、うまくなるための”コツ”を掴みやすくなるような内容が多いと個人的に感じました。
「がむしゃらに練習しているけど成長している実感が沸かない」
「なんだか今の自分のプレーや感覚がしっくりこない」
という選手にとっては多くの気づきを与えてくれる1冊になるかもしれません。
8位:『仙台育英日本一からの招待 幸福度の高いチームづくり』須江航・著
第8位は『仙台育英日本一からの招待 幸福度の高いチームづくり』須江航・著です。
2022年の夏の甲子園で東北勢初の甲子園優勝、2023年夏にも甲子園準優勝を果たした仙台育英学園高校野球部で監督を務める須江航(すえわたる)氏の書籍です。
少年野球にも通じる部分が多くある
仙台育英高校での実際の取組みや目標の設定方法などについて書かれているため、技術的なレベルは高校生以上のため少年野球にそのまま落とし込めるものではありませんが、おすすめしたいと思った部分は「選手一人一人に向き合う姿勢について気付きの得られる内容が多い」というところです。
言葉の大切さ、指導者としての関わり方、教育者としての関わり方など、高校生に限らず全ての年代に共通しているなと感じました。
近年話題として挙げられることの多い「勝利至上主義」への考え方や「根性や忍耐力」などについても触れられています。
微妙なニュアンスをうまく言語化してくれている
須江監督自身が言葉や相手に伝わることを大切にしていることもあり、「私自身は説明しづらいな、伝えるのが難しいな」という内容についても見事に腑に落ちる表現で書かれていました。
「青春は密」「人生は敗者復活戦」など名言として挙げられる言葉も多く残していますが、それ以外にも様々な感情や思いが正しく凝縮されたであろう言葉が多くありました。
内容に共感できるかどうかは別として、少なくとも指導するにあたっての自分自身の表現の仕方、言葉の使い方、伝え方にヒントを与えてくれる1冊になると思います。
9位:『プロフェッショナル投手育成メソッド 一流選手へ導く“投球メカニズムとトレーニング”』工藤公康・著
第9位は『プロフェッショナル投手育成メソッド 一流選手へ導く“投球メカニズムとトレーニング”』工藤公康・著です。
プロ野球では投手として通算224勝を達成し、ソフトバンクホークス監督としても日本一を達成した実績を持つ工藤公康氏の書籍です。
「1年でも長く野球を続ける」「プロで活躍して、結果を残す」そのためにはどんな考えが必要で、どんなトレーニングをするべきなのかについて、実際に現場でも取り組んできた内容をノウハウとして詰め込んだ1冊となります。
18歳以上を対象とした内容だが・・・
本書は著者自身が対象を18歳以上としていることもあり、トレーニングの内容や言葉の表現は大人向けになっています。
しかし、なぜ18歳以上としているかについても理由が書かれているため、逆に言えばこの本の内容(特にトレーニング)については少年野球の段階では無理に取り入れる必要が無いと判断する材料にもなります。
第1章「投手に必要な3つの柱」だけでも読む価値あり
私が対象が18歳以上となっている本書を”読んで損はなし”に分類したのは、投手、ひいては投げ方を指導するのであれば第1章の「投手に必要な3つの柱」の内容は是非読んでもらいたいと思ったからです。
近年では高いパフォーマンスを実現するために、様々な技術や動作について解説されていることが多いと感じていますが、本書では投球技術の根底として「リズム・タイミング・バランス」という存在を挙げています。(第2章以降では専門的な技術の解説が入ってきます。)
この第1章だけを取り上げたとしても、選手として本書を読んで実践に移すのは18歳以上が対象であったとしても、指導者として読むのであれば対象が少年野球の指導者であっても大いに学びになる1冊だと思いました。
10位:『卒スポ根で連続日本一 多賀少年野球クラブに学びてぇ! これが「令和」の学童指導』トータルテンボス 藤田憲右(ふじたけんすけ)・著
第10位は『卒スポ根で連続日本一 多賀少年野球クラブに学びてぇ! これが「令和」の学童指導』藤田憲右・著です。
対話形式で難しい理論などもなく、とても読みやすいです。
実際の体験談に基づくお話で野球指導者としてはイメージしやすいと思いました。
取り上げられている内容をそのまま全て実践することは難しいかもしれませんが、学ぶことはたくさんあり、部分的に実践していくことはできると思います。
正直この本で取り上げられている辻さんと同じことをしようとするのは、簡単ではありません(という内容もあります)。
QRコードで動画が見られる
本書では、動画のQRコードがあり、練習内容や実際に教えている場面を動画で見ることもできます。スポーツは言葉で説明されるよりも、実際の動きを見たほうが絶対理解度は高くなりますもんね。
文章だけで伝えるよりも、正しく伝わりそうで良いなと思いました。
33年の経験に基づく内容
33年間の経験に基づくお話で、上手くいかなかったことから上手くいったことまで、実験的に取り組んだ結果を話されていて、納得できる内容もありました。
現在も試行錯誤しながらということで、完全に体系的にできるところもあれば、「~と思う。」という推測の部分も半々ぐらいでした。
11位:『少年野球で、子どもをグングン伸ばす47の教えためのアドバイス』桜井一・著
第11位は『少年野球で、子どもをグングン伸ばす47の教えためのアドバイス』桜井一・著です。
保護者の悩みに返答
指導者だけではなく、保護者の方にとっても参考になる内容だと思いました。
保護者のリアルな悩みや質問に返答する形式で書かれており、難しい表現もなくとてもわかりやすいと思います。
本書は大きくわけて「指導するうえでの子どもとの接し方」「投球指導」「打撃指導」の大きく3つに分けられています。
質問形式ということもあり、1つの質問に対しての回答は丁寧に書かれていますが、指導全体として体系立てて書かれているわけではありませんでした。
指導内容というよりも指導するに当たっての大人の心構えの部分を中心に書かれています。
研究などに基づいた内容ではなく、筆者の経験則や主張を基に書かれていますが、なぜそう思うのかという部分も併せて解説されています。
子どもに対してどのように接するのか
子どもにとって少年野球はどのような存在なのか、少年野球の指導をするにあたって、大人は子どもにとってどう接することが望ましいのか、指導する大人側のの方針、考え方について書かれているため、特別な能力がなければ実践できないという内容はなく、意識すれば十分実践できる内容だと思います。
その他:12位〜19位
12位:『コントロールの極意』吉見一起・著(2022/5/27)
第12位は『コントロールの極意』吉見一起・著です。
抜群のコントロールを誇った元中日ドラゴンズのエースである吉見一起氏の著書になります。
何かひとつでもコントロール向上のヒントやきっかけを掴んでもらいたいという思いが込められた一冊になります。
著者自身の感覚や取り組んだこと、合わなかった感覚、なぜコントロールを求めたのかなど詳しく書かれています。
内容としては学びの多い一冊で早速取り組んでみたいという内容もありましたが、感覚としては中学生以降の投手に対して視野を広げる書籍だなと感じたので、少年野球指導という観点では少し時期が早い内容と思いその他に分類しました。
投手としてレベルを上げたいと意気込むプレーヤー自身が読む一冊としては大いに役立つと感じます。
13位:『高校野球界の監督(スペシャリスト)がここまで明かす!投球技術の極意』大利実・著(2021/7/20)

第13位は『高校野球界の監督(スペシャリスト)がここまで明かす!投球技術の極意』大利実・著です。
高校野球界や大学野球界で実績を残している指導者を取材し、どのように投手育成をしているのかについて、それぞれの視点で語っているのをまとめた1冊になります。
本書の冒頭文にも
「本書を読み進めていく中で、「この練習を試してみたい!」「この感覚は面白い!」といった発見や刺激がひとつでもあれば、著者冥利に尽きる」
とあるように、何が自分自身に合うのか模索したり、今までになかった発想や視点を生み出すにはいいヒントに巡り合える可能性のある1冊だと思いました。
小学生でも試してみていいんじゃないかという内容がないわけではないですが、基本的には専門的な内容もあり、高校野球で高いレベルで勝負をすることを前提としているためその他に分類しました。
小学生期についての技術的な内容やトレーニングは上位の書籍から学べば十分であると思います。
14位:『小学生からはじめるウエートトレーニングあり⁈なし⁈ 筋トレすると背が伸びないはもう古い!!』大浜海・著(2024/5/25)

第14位は『小学生からはじめるウエートトレーニングあり⁈なし⁈ 筋トレすると背が伸びないはもう古い!!』大浜海・著です。
小学生でウエイトトレーニングを行うことの効果や、適切なトレーニングの強度について、日本、アメリカ、ヨーロッパでの研究を基に説明している1冊です。
本書は文章のみで、具体的にどのようなトレーニングを行ったら良いのかなどについては分かりやすくまとめられている訳ではなく、実践的ではありませんでした。
小学生のウエイトトレーニングに関して疑問を持っている人にとっては、知識のインプットとして活用できる本と思われます。
15位:『DVDで差がつく! 小学生の野球 最強のポイント55 (まなぶっく)』大前益視・監修(2018/3/5)
第15位は『DVDで差がつく! 小学生の野球 最強のポイント55 (まなぶっく)』大前益視・監修です。
本書はリトルリーグ(少年硬式野球)で世界一の実績を持つ武蔵府中リトルリーグで監督を務める大前益視(おおまえますみ)氏が監修した書籍です。
映像付きで少年野球で身につけたい技術や上達のコツなどを解説しています。
書籍では写真を多く使用しながら説明されているため理解しやすい内容になっていました。
その他に分類した理由としては「実際にプレーをする子ども自身が自発的に見て学ぶことに重きをおいているような内容と感じた」「本書の内容を指導として落とし込むには根拠が薄いと感じた(小学生にもわかりやすい説明をしている分致し方ないとも思う)」からです。
上達のコツなど、ヒントになるであろう内容もあったのですが、指導者としては上位の書籍でカバーできる内容も多いと感じました。
16位:『野球データ革命』森本崚汰・著
第16位は『野球データ革命』森本崚汰・著です。
近年話題となっているデータ野球に関して書かれています。
取り上げられているデータはとても興味深く、練習の目標も立てやすくなる内容も多くありました。
しかしながら小学校指導という観点からみると、目指すレベルが高すぎる内容だったため「その他」として分類しました。
高いレベルを目指す中学生、少なくとも高校生以降の選手にとっては参考になる書籍だと思います。
17位:『トクサンTVが教える 超ピッチング講座』アニキ・著(2019/11/22)
第17位は『トクサンTVが教える 超ピッチング講座』アニキ・著です。
本書はYouTubeチャンネル「トクサンTV」のプロデューサーを務めるアニキ氏が「少年野球から草野球まで使える独自のピッチング理論を解説」している書籍になります。
ピッチングに特化した内容で、レベルアップのためにとても気付きが多く得られる書籍と思いました。
また、内容についても写真付きで視覚的にわかりやすく、QRコードで詳しい解説動画も見れるようになっています。
しかしながら、内容のレベルとしては中学生以降が最適ではないかという感想を持ったため、その他の分類にしました。
少年野球を終え、これから中学生になっても野球を続けていくというタイミングで選手自身が読むのにはとても参考になる書籍だと思います。
18位:これで差がつく! 勝つ!軟式野球 上達のコツ50 (コツがわかる本!)名古屋光彦・監修(2018/6/5)
第18位はこれで差がつく! 勝つ!軟式野球 上達のコツ50 (コツがわかる本!)名古屋光彦・監修です。
本書は大学軟式野球日本代表の監督経験(2009年〜2014年)を持つ名古屋光彦(なごやみつひこ)氏が監修した書籍です。
写真付きでわかりやすくまとめられていると思いましたが、説明がざっくりとしていて、何をどう練習したらよいかなどについての説明があまりなかったことや、対象が少年ではなく大人向けであると感じたことなどから”その他”の分類としました。
19位:『野球選手を育てる教科書 少年野球』
第19位は『野球選手を育てる教科書 少年野球』emi著です。
本書は全部で11ページと文量としては多くはありません。
内容として、興味があるだけにもっと具体的な事例や根拠を深堀して欲しいなと言う想いがありました。
本書で取り上げられていた褒め方や褒めるポイント、挑戦(試合出場)の機会を与える判断基準等の具体的な内容があれば、参考にしたいなと思いましたが、残念ながら書かれていませんでした。
さいごに
これからも、自身が学ぶ中でいいなと思った本は随時ランキングにして更新していきます。
最後まで読んでくださりありがとうございました。
みなさんのこれからがより輝くものになりますように。
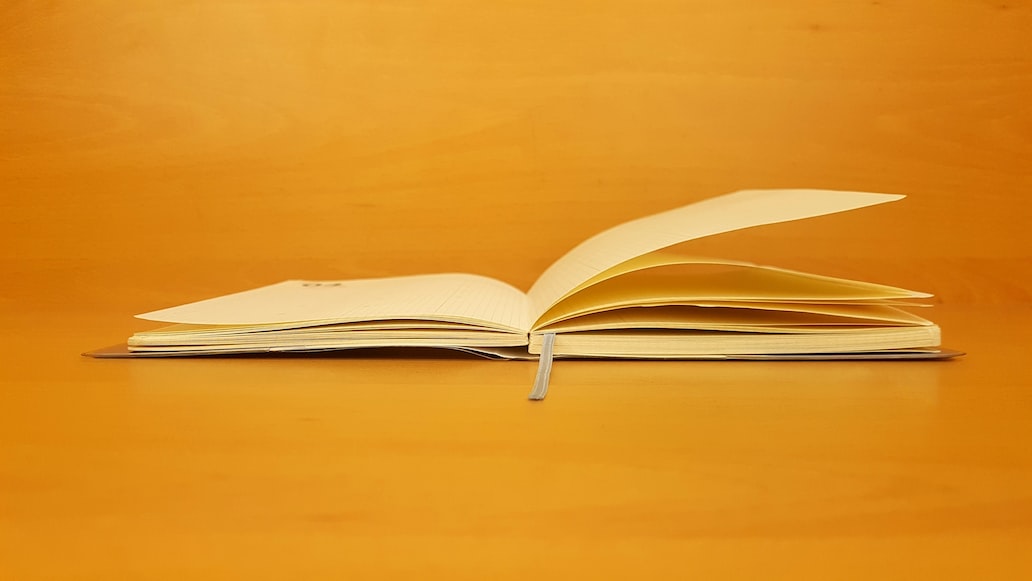


コメント